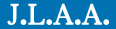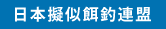ルアー釣りの面白さ
作家・開高 健
昨年の夏、ドイツで遊んでいるときに、バド・ゴーデスベルグの釣道具屋のおじさんにルアー釣りを教えられ、それから病みつきになり、今年はアフリカと中東の最前線を観察する旅の途上、アラスカをふりだしに、ずっと釣り歩きつつ旅程を追っていきました。
ルアーには見るからに精巧なのや、チャチで軽薄なのや、それこそ出来と種類はゴマンとあるのですが、結果は外見では分かりません。 いちいち試してみるよりほかないようです。
しかし、小生の経験では、その土地、その土地で作られたものはやっぱり一度はためしてみなければいけないということがいえそうです。 どれほどチャチで軽薄な外観であっても土地の釣師が作っていたなら、それは正しいのです。
アラスカの荒野の河に腰まで浸かってベーリング海から上がってくるキング・サケを釣ったのは生涯忘れられない経験でした。 キングは数あるサケ属のなかでも一匹ずつ闘争のしかたが異なるのでアングラーはその瞬間瞬間に臨機応変の技術をフルに動員しなければならない。 だから釣りのなかの釣り、王の王とされています。 これは靴ベラくらいもあるスプーンを投げ、ゆっくりゆっくりとひいて誘いこむのですが、悪魔のマークのついた《ダーデヴル》と、それを真似た《フラッシュ・ベイト》が最高でした。 《ダーデヴル》はスプーン専門のメーカーと思われますが、塗りがしっかりし、泳ぎかたが精巧で、評判はたいへんいいようです。
スピンナーではメップスが王座でしょう。 あるアメリカの釣師の論ずるところではメップスの模造品はゴマンとあるけれど、ついに本物には負ける。 こんな簡単なものマスプロ品のくせにどうしてそうなるのか、わからないといって脱帽しています。 プラグではフィンランドの手製のラパラに絶大な人気があります。 これは静水でも激流でも決してひっくりかえることがなく完璧なバランスで泳ぎます。
ライフ誌が"魚の見のがせないルアー"といって3頁にわたって特集をしたことがあるらしく、また、アメリカの主な釣り雑誌が主催するコンテストの首位は軒なみこれでさらわれているようです。
スエーデンのアブ社の山荘に招待されて私は水銀の光るような淡く、かつ華麗な白夜の夏をたのしみましたが、同社の作品では、トビー、ドロッペン、ハイローなど、名作がたくさんあります。 ことにトビーは河でも海でも、こと相手が肉食魚でありさえすれば、ほとんど万能といっていいのではないかと思われる逸品で、いろいろな場所で使ってみてそのことがよくわかりました。 ついたその日に山荘のしたを流れるモラム川で私は74センチのパイクを釣りましたが、これもトビーでした。 するとアブ社の輸出部長が、わるくない、いい腕だといったあと、ハムレットの”To be Or not to be・・・”にひっかけ「to buy or not to buy・・・」と一句とばしました。
ミミズや小魚などの自然餌はほっておいても魚が食べるのですから、それで魚を釣ってもあまり自慢にならない。 釣れなければ不思議だ。 しかし、釣りはやっぱり魚との知恵くらべ、だましあいでなければ、ほんとの面白さがでてこない。
芸術とは反自然的な行為なのだ。 釣りが芸術なら、やっぱり反自然的でないと、イカン。 というわけで、精巧、軽薄、珍奇華麗、じつにその工夫の妙においてとどまることを知らないルアーの大群が出現しつつあるわけです。
ルアーを"食いついたものかどうか"とさいごまで疑いつつ追っかけてきて私の足もとあたりまで迫り、"やっぱりノセモノだった、ガセだ、かかってたまるかい"と、魚はくるりとひきかえしていく。
なかにはピシャリと尾で水をたたいていくのもいる。 その横顔のニクイッたらありません。 河のなかで地団駄踏みたくなります。 思いぞ屈してこころがほぐれない夜は、机にルアーを並べ、この傷はあの河だった、あの傷はこの魚だったと、野生の宝石の追憶にひたる。
また、油砥石で、いつでかけるとも知れない日のために鉤を研ぎ、爪にあてて試してみる。
これは無益な純粋ともいうべき遊びでしょうが、現代のようにすべての物と言葉がベタベタと指紋がついてよごれはててしまった時代には、ふとした瞬間ルアーがオモチャだといえなくなってきます。 私はたまたまドイツで教えられたのでしたが、日本へ帰ってきてみると、桐生の常見氏とか、藤沢の金子氏とか、もう何年も以前からこの釣りに凝っている名人がいると知らされておどろいてしまいました。 ほかにもたくさんの鬼や亡者や、気ちがいや、手製の名匠がいるというのです。
こういう会ができて、それら鬼、亡者、気ちがい、名人、上手、女房泣かせ、半ば子供衆の脳を持った大人衆と、半ば大人衆の脳を持った子供衆とが、めいめいの経験とホラ話を持ちよって百家争鳴するのは、たまゆらこころほどけることだと思います。
人間嫌いの芸術家はみんなこい。